| その5 宗像家の終り | ||||
≪宗像記より≫ | ||||
氏貞の東進大きな犠牲を払いながらも大友氏と和睦し、立花道雪とも縁戚関係を結んだ氏貞は、西境の立花城からの攻撃に心を使う必要も無くなり、東方の固めに力を注いだ。境界線をめぐっては、しばしば山鹿城の麻生元重と争っていたが、天正6年(1578年)四月、遠賀平野に軍を差し向けた。
| ||||
宗像宮造営遷宮大友氏との和睦で訪れた平和の時を逃さず、氏貞は辺津宮本殿を再建造営した。辺津宮は弘治3年(1557年)四月に社殿・神体・神宝が焼失していたが、戦乱続きの中で再建出来ず、そのことが氏貞の心を悩ませていた。永禄7年(1564年)になって、京都の仏師が地島に着岸し、三社の御神躰を彫刻し奉る。早速仮殿造営に取り掛ったが、乱世続きで資金不足となり頓挫した。
そこへ中国明への貿易船が帰国途中に津屋崎沖で難破した。室町将軍足利義輝から返還要求が来たが、漂着物は宗像社の造営費用に充ててよいとする慣例があることを主張してこれを収得。このおかげで仮殿が出来、続いて御本社造営にかかろうとする。ところが、永禄10年からの騒乱で再び延期になった。 このたび大友氏との和睦に及んで、念願叶い天正4年(1576年)に造営開始。天正6年(1578年)六月朔月に遷座式が執り行われた。大友氏に下ったことで多くの屈辱はあったが、本殿再建の大事業をすることができたのも、戦が減って蓄財がすすんだおかげであろう。又、氏貞はこの造営に当たり、領民を動員し、諸役を負担させた。領の堺のはっきりしなかった遠賀に兵を出したのも、この大事業にかかわってのことであったろう。天正6年に本社は完成したが拝殿楼門他祭祀を行う殿舎末社などは復旧することができなかった。その願いは氏貞の手によって実現しきれず、天正15年(1587年)、筑前領主となった小早川隆景の手に引き継がれる。 占部氏系伝貞保の危機
宗像家の四家、占部・大和・吉田・高向は特に四任(しとう)と呼ばれていた。宗像に清氏卿が京より下向された折、お供して下ってきた占部尹安、吉田知弘、大和秀一、高向良範の子孫であるという。 さて、大和が二の座についたのを見て占部姓の者達が騒ぎ出した。「四任においては、古来より一)占部、二)大和、三)吉田、四)高向の順になっているにもかかわらず、今度の大禮の晴れの庁座に大和が二の座について、二献の酌をとるのはおかしい」というのだ。彼等は八郎貞保に「今度のことは今までの方式に背くことであるから、黙って見過ごすわけにはいかない。その方(貞保)は力量があるのだから大和を引き立て追い出せ。」とわめく。 これに対し、貞保は「大和の着座に関しては社務よりの仰せであるからどうすることも出来ない」と言うが、皆が引き下がらず、貞保を説得する。ならばと、ついに大和を引き立て追い出してしまった。 しかし、これに対し祈祷の座を騒がせ、神事の妨げをしたとして氏貞の立腹は意外に激しく即刻貞保に岳山への出仕を差し止められた。その後同姓越後守賢安は社役の長として、氏貞に事の次第を申し開きし、十月には大和の家が断絶となった。しかし、貞保の所行は許されず、許斐城を召し上げられ、貞保の姉婿にあたる許斐左馬太夫氏備に預けられた。更に上八(こうじょう)の百八十七町は免れたものの、許斐の領地三百町は召し上げられた。貞保は父を祀った今宮とともに屋敷を上八に移して、ここに移り住んだ。 大和・高向の事
大和・高向の二家も清氏卿以来の旧臣である。氏貞が七歳にして宗像家を継いだ折、この二家は陶晴賢について鍋寿丸(後、氏貞)擁立の側に立った。もう一方の後継者候補、菊姫とその母が殺害された事件のことは将軍家の耳にまで入り、前代未聞の悪逆であるとして、事の解明を大内氏に仰せ付けられた。大内義隆の跡を継いだ義長は四任の人々を召喚し、占部・吉田・大和・高向はともに山口に向かったが、途中大和と高向は進退谷まって逐電した。占部・吉田は山口に行き、無事に申し開きをして帰国した。その後氏貞は逐電した二人を探し尋ねていたがみつからず、大祭の時にいたり、ようやく大和を探し当てたのであった。(宗像記には大和としか書かれていないが、占部氏家系図には大和左衛門尉秀尚とある。)高向は結局最後まで見つからなかった為に宗像家の一族深田氏が名代として着座した。
古来、天下の御祈祷の際には氏貞が勅使の座につくのと同様、四任の子孫も各座につくようになっており、つくべき人がいない時にはあえて他人は座につかない慣わしであった。それを理由に氏貞はこの二人を懸命に探させたが、氏貞の心には今一つ彼等を捜したい理由があった。主人を殺害した大罪人との汚名をきた二人だが、実は氏貞にとっては自分を応援支持してくれた大事な家臣であったのだ。それで、この祭禮を機に彼等を召し出そうと思ったのであった。 しかし、占部氏にとっては自らが第四の座であり、大和が第二の座につく事はとうてい承服できない事であった。高向の替りとして座についた深田氏は、宗像家の一族であるから不服は無い。又、吉田氏は宗像家臣の内でも最たる重鎮であり、占部氏とは縁戚関係を以って深く結びついている。しかし、大和に関しては納得がいかなかった。大和を引き立て、しかも氏貞にそれを責められると、「神は非礼を受け給わず。大和はその身に科(とが)のある者なるに、この大禮の座に罷(まか)り出ん事、有べくもあらず」と申し立てる。公の場で面罵(めんば)され、大和は面目を失った。それだけではない。大和の出席は氏貞が定めた事であったから、氏貞の怒りもひとしおであった。この後大和は再び行方知れずとなった。高向・大和の子孫が絶えたのも彼の御霊の祟りだと人々は噂したという。(その後大和断絶を惜しみ、寺内秀郷の嫡子を大和姓とした) 占部賢安
吉田氏系図
┌女
┌占部尚持妻(後妻となる)┴貞保
土佐守────┬社家 重致(伯耆守・法名宗金)─┬女子(占部賢安妻)→──┐
(勘解由左衛門)├勝致(伊賀守) ├貞棟(貞能・内蔵太夫) │
└守致(弾正忠・土佐守) ├貞乗(大炊助) │
├長閑(修理入道) │
├女子(深田氏榮妻) │
└貞昌(弥太郎) │
┌─────────────┘
占部相安(伊豆守、武役兼任)─尚賢─賢安(越後守)─種安(弥次郎、大膳進)
占部氏は一族の中で社役と武役に別れていたが、占部豊安−尚安−尚持−貞保の一家は武役の流れであり、他に社役の流れとして占部相安−尚賢−賢安−種安の一家がおり、中でも賢安の名は文献にも頻繁に登場してくる。宗像記などには賢安を「社役の長」と記載しているが、豊安の家系が嫡流であるとし、後者賢安の家系は庶流であるとしている。
占部賢安の詳しい系図は残っていない。
反大友色を前面に出し、大内氏や毛利氏に一途に従った尚安の一家とは異なり、賢安は中立を守っていたと思われる。賢安は舅(しゅうと)吉田重致とともに常に宗像家中枢におり、尚安の一家が浮き沈みが激しかったのに対して、宗像家が滅する最後までその権勢は変わらなかった。尚安の一族が忠節と武勇を一義とする武家だったとすれば、吉田重致は政治的能力に長け、賢安はこの義父(舅)によって育てられたといっても過言ではなかろう。吉田重致は、もともと吉田の庶流であったが、後に総領家に成り上がった人物である。鍋寿丸(氏貞)の相続騒動の時にも、この二人は早期に復権を果たしている。 尚安一家の性格からすれば、吉田重致のやり方が気に入らないことも多かっただろうと推察する。しかし、一徹な性格な故に不利益を被る事も多く、そんな時には吉田重致や占部賢安に助けられることも多かった。 一方、毛利元就は、尚安一家ほど信頼を置いていなかったらしい。 深田氏実・占部賢安・吉田重致の嫡男は氏貞の娘(最初の妻との子)とともに長門の四ヶ小野に人質となっていた。大友氏との和睦の折、この人質を見捨てる事が選択肢にあげられているが、氏貞は是を良しとせず、智略を以て取り返し永禄12年十二月二日に宗像に帰還している。 争乱再び宗像で大禮が行われている頃、南から北上してくる島津軍に対し、大友宗麟が軍を日向に向かわせていた。当時、宗麟は本拠地豊後をはじめ、豊前・筑前・筑後・肥前・肥後の6カ国を支配する九州最大の大名となっていたが、南より島津氏が日向を侵食してきていた。重臣達の反対を押し切って進軍させた宗麟だったが、耳川において壊滅的打撃を蒙り敗北する。九州の勢力地図が塗り替えられようとしていた。 天正6年(1576年)の十一月に大友軍が日向遠征で島津軍に大敗すると、東へと勢力を拡大する肥前の龍造寺氏に筑前の秋月氏が同調し、肥前の筑紫広門や筑前の反大友の動きがにわかに活発化する。大友宗麟にとっては、筑前の押さえを立花城の立花道雪、岩屋城の高橋紹運の両氏の力に頼るしかなかった。岩屋城(太宰府市浦城)は猛攻を受けたが高橋紹運はこれをよく防いだ。宗像氏貞はこれら反大友の動きに同調しようとした。宗像氏系図には「天正7年己卯年、秋月種実、同照種、及び木村板波坂田桑原等、九州之士、氏貞一味、属毛利家…」とある。天正8年(1578年)五月、大友宗麟(立花道雪とも)は鷹取(直方市鷹取山)城主毛利鎮実に、宗像氏の猫城を攻めさせた。立花道雪との和睦をいいことに、麻生氏より猫城を奪い領地の確保にあたった宗像氏である。この時は大目に見たが、大友氏の衰退を見て取るや秋月氏を中心とする反大友勢力に合流しようとするのは許せない。そうした動きをけん制する意味か、或いは裏切りに報復する意味かはわからない。とにかく、宗像軍はこれを必死に守りぬいた。道雪の脅かしが効いたのか、その後和睦を破棄する動きも無く落ち着いたかに見えた。 小金原の戦い筑前の秋月種実は早くから龍造寺隆信と通じ大友方の鞍手郡鷹取城主森(毛利)鎮実と攻防を重ねていた。天正9年(1581年)11月、森鎮実は立花道雪へ食糧・弾薬等の加勢を求めた。道雪はすぐに糧米と弾薬を500余りの兵に輸送させ鷹取に向かわせた。途中通る若宮にはかつて西郷を追い払われて移り住んだ西郷党の諸家がおり、これらの人々が遺恨を晴らそうとするのを懸念して道雪はあらかじめ宗像氏貞に書を送り、領内通行の了解を取り付けていた。しかし、西郷党の恨みは深く、氏貞の命に叛いて帰途に着いた立花勢を在地の人々ともに襲ったのである。ここに秋月の援軍が笠木城より合流し、戦いの規模は拡大した。両者多数の死者を出したが、小金原の激戦も日没とともに終わった。この戦で立花方の名の有る武士30名程の命を奪ったが、その他西郷党の得たものはただ味方の犠牲のみであった。 宗像氏貞はこれを「一握りの家臣の暴走」で片付けようとする。しかし、笠木山より秋月軍まで駆けつけ、意外にも大戦(いくさ)となったこの戦いで道雪は貴重な戦力を多数失ったのである。遺恨のある西郷党の襲撃は予想していたものの、氏貞に対する疑念が湧く。 一方宗像では立花からの攻撃が今日か、明日かと心休まる日がなかった。攻撃あらば、許斐より内には一歩も入れさせぬと思いながら、こういう時には神力を仰ぎ奉るのが古来の例である。早速奉行人を初め22人連署して願文を神宮に奉り、社敵征伐を願う。願文の日付は天正10年(1582年)三月七日である。 一方天正10年(1582年)三月十六日、腹の虫がおさまらない道雪は小野和泉らに500余騎を従わせ、宗像に向けて出陣させた。宗像氏貞は人を送って、軍勢を引き上げさせようとするがかなわず、八並・吉原あたりで戦となった。しかし、不思議にも立花勢はそれ以上深く宗像に攻め込まなかった。「宗像記追考」ではこの時の願文を掲載し、「立花から寄せ来たが小勢にて大敵を退け、大したことにもならなかったのはこの神力の霊験あらたかなるゆえ」としている。大友氏の衰退によるものか...。道雪自身すでにこの時70歳を越えていた。島津氏が南からじわじわと上がって来る。又1つの時代が終わろうとしていた。 | ||||
氏貞の死
天正14年(1586年)三月四日、氏貞が逝去した。氏貞は以前より度々患っていた様である。しかしこの時は御家人達が心を尽くし精を尽くして処々の宿願、様々な祈祷を行い、又医療にも手を尽くしたが、次第に病状が悪化し、食事もままらなくなり42歳で他界した。この時傍に付き添っていたのは、晴気次郎と医師良梅軒他ごくわずかの人数であった。この晴気次郎は、大友氏との和睦の際に氏貞が命を奪った河津隆家の息子である。氏貞は自ら回復の望めないことを悟り、奉行達に使いを送った。 「明日にも死ぬようなことがあれば、深くこれを隠して、隣境より領分を押領されぬようにしなければならない。死骸は夜中密かに承福寺に送り、仏事など執り行ってはいけない。三年の間はこれを隠し、以前のごとくに振舞わねばならない。家督がしかと定まり世間に逝去の事実を明らかにした後に、百僧供養して、千部の妙典追福を執行せよ」との遺言を伝えさせた。奉行達はこれを聞き、皆涙に咽び返答申し上げる者も無く、ただ手も力も失い果てた様子であったという。 遺言に従い、奉行達は御家人にも、ただ「ご病気中」とだけ伝えるばかりで何も知らせず、死骸は竹皮籠に納めて、人の寝静まった夜更けに運び出し、上八の承福寺に納めた。院号は「即心院殿一以鼎恕(いちいていじょ)大居士」。占部右衛門が氏貞の亡骸を背負って蔦ヶ嶽城から承福寺まで運んだという。遺体を運んだのは占部貞保であるという説があるがどうであろうか。「宗像大宮司天正十三年分限帳」には野坂庄衆として確かに占部右衛門(神九郎)の名がある。野坂庄衆には筆頭として最後まで氏貞に付き添っていた晴気次郎がいるが、次郎が村内の人物に頼んだ可能性は大いにある。ただ、上八は貞保の村であるから、実際に運んだのは誰だとしても、この埋葬に占部貞保が関与していなかった訳はない。氏貞は、承福寺の門前にある乙尾山に葬られ、現在も御塔が修復され残っている。乙尾山には占部豊安や尚安の墓がある。今も一族が主君の墓を守っている。
| ||||
島津軍の北上と秀吉の九州遠征天正13年(1585年)七月、関白に就いた羽柴秀吉は四国平定を終え、同年十月、島津義久と大友義統に停戦令を出し、翌年14年の三月には九州国分構想を提示した。十二月には、太政大臣に任ぜられ豊臣を名乗る。しかし、肥前の龍造寺隆信を討って勢いづく島津義久は、秀吉の勧告を蹴って進撃を続ける。今や島津の台頭を自力で食い止めることができなくなった大友氏は、豊後の城の他筑前の立花城・岩屋城を献じて秀吉の幕下に入り、秀吉の援護を待つしかなかった。当時筑前の大友氏直轄の城は、岩屋城と立花城の二城になっていた。宝満城はすでに筑紫広門に奪われていた。立花城の立花道雪は既に病没しており、岩屋は高橋紹運、立花は道雪の養子となった高橋紹運の子統虎(むねとら)が守っていた。宝満城の筑紫広門は後に大友方についている。古処山の秋月種実は初めから島津氏についていた。 天正14年(1586年)六月島津軍は東西二手に分かれて進攻を開始。西廻りは筑後から筑前を目指し、東回りは日向より豊後へ攻め込む計画であった。島津義久の弟忠長が率いる西廻の軍勢は途中、周辺諸将達を加えながら筑後へ向かい、六月には筑後の高良山を落とし、肥前からの援軍と筑前からは秋月、原田などを加えて七月にいたった。天正14年七月六日には筑紫広門を攻めて勝尾城は落城。広門は島津軍に降った。七月九日高橋紹運・立花統虎父子は迫り来る敵を前に、秀吉に救援を求めた。 大友氏の勇将高橋紹運は岩屋城に立て籠もり、押し寄せる大軍を相手に壮絶な戦いを繰り返したが、紹運の人柄に、脱落する家臣は一人も居らず、最後は皆自刃して果てたという。七月二十七日未明、ついに城は落ちたが、島津軍もこの戦闘で多大な犠牲を出した。岩屋城を落とし、ようやく筑紫氏との相城になっていた宝満城を手に入れ、残るは立花城というところで、秀吉の援軍がかけつけた。八月二十四日、毛利勢が豊前に上陸したとの報せをうけて、島津軍は一斉に撤退した。自らの玉砕によって長子立花統虎を守り抜いた紹運だが、秀吉は父の勇姿を称え九州平定を助けた功によって、後にその子立花統虎を筑後柳川の大名に任じている。 この時期発給された文書から、宗像勢が渡海した毛利勢を助け、麻生氏とともに門司や小倉で毛利軍に合流して戦ったことがわかっている。又、島津方であった秋月種実が秋月の端城から退却した時にはそれを追撃している。 占部氏系伝失脚の裏側
貞保は宗像宮造営遷宮の折に氏貞の怒りをかって後、上八の自宅に引き籠っていた。若気の至りとはいえ先代からの功を思えば理不尽にも思え、悔しくもあったであろうが、とにかく御勘気を蒙った身であるから何事にもおとなしく構えて日を過ごした。伴う人も無く、吉田右馬助貞房に連歌の手ほどきなど受けながら朝夕の慰めとしたという。 宗像記などを読めば貞保は何もかも失った雰囲気であるが、天正年間の分限帳をみるかぎりでは、許斐を失った後も上八187町8反をそのまま領しており、これは宗像家臣の中でも断トツに多い領地である。重臣吉田重致の長男でも140町であるから、貞保の家がいかに宗像家中で力があったかがわかる。しかし、祖祖父の代で許斐の城を再建し、以来許斐の歴史は貞保の一家の歴史でもあった。ここを守ることにより、宗像家の安泰を守ってきた誇りが、あろうことか命を捧げてきた主君によって完膚なきまでに踏みにじられてしまったのだ。その後、宗像家が戦に出た時も貞保の名はそこにない。許斐城を失ったことがどれほど大きい衝撃であったかがわかる。 氏貞は何故これほどまでに処置したのだろうか。これには大友氏が係っていたのではないかと筆者は思う。大友氏にとって西郷衆、特に亀山城の河津氏が目障りだったのと同様、宗像への入口許斐山に強硬な反大友派の占部尚安一家が陣取っていることは極めて不都合なことであったに違いない。和睦の折、河津隆家を氏貞に殺害させた時、ともども許斐の占部一家も始末したいところであったに違いない。しかし、尚安の婿だった河津隆家の殺害にとどまり、それ以上宗像家旧臣の尚安一家に手を出すことはできなかった。 一方、氏貞は妹を立花道雪に嫁がせ、大きな犠牲を払ってまで得た平和を壊すことはできなかった。近年、遠賀の領地を確保できたのも西の立花氏が黙っていたからである。宗像家の中央で反大友の色を強くしてあらぬ疑いをかけられることも避けたかったに違いない。先代からの重臣であった尚安もすでに亡くなり、自らが加冠した貞保に対しての気安さもあったであろうか。尚安の婿の河津隆家を殺した替わりに孫の晴気次郎(隆家の子)を最後まで側に置いて愛したり、貞保から許斐の城を召し上げたが他人に渡さず姉婿の許斐氏に預けたのも、氏貞の尚安一家に対する心遣いだったのかもしれない。 貞保の心
氏貞が亡くなる前、天正12年には貞保は筑後守を許された。占部家系図には天正14年とされているが、宗像記追考で本人が天正12年としているのでそれが正しいだろう。天正9年(1581年)の若宮での戦い(小金原の戦い)をきっかけに大友氏との和睦が崩れ、天正11年(1583年)には立花道雪・高橋統虎の攻撃を受けた。天正12年3月には立花道雪に輿入れした色姫も亡くなり、立花氏・大友氏への気遣いはもはや必要なくなったのだろう。それとともに貞保が復権を果たした。 ところが貞保はこの後も筑後守を名乗らず「この身には八郎が似つかわしい」として八郎を名乗った。重臣達と名を連ねる時でも八郎貞保と署名する。失脚の傷が癒えていなかったのだろう。占部家系図では、着座の一件で氏貞より下された命に対し、貞保は心服しがたく、召し出しにも応じずに上八に引き籠ったと書かれ、貞保の憤懣やるかたない様子が描かれている。一方宗像記追考で語られる貞保の思いはもう少し複雑である。若輩の失態と悔やまれることあり、氏貞のご勘気ももっともと思う。しかし、場所と時が悪かったとはいえ、着座の次第について納得のいかないのも事実である。それにしても、忠義第一の自分に対して何とも厳しい御沙汰である。同族占部賢安の説得により大和は断絶となったが、占部側の主張にも一理ありとなったにしては許斐の領地は召し上げられたまま戻ってこない。そもそも大和を追い出したのも自分が願っての仕業ではない。同族たちに煽り立てられてやむなくしたことである。いやいや何はどうあれ主君の定めた御沙汰であれば、ただ従うのが道理と自分を諌める。後悔・憤り・口惜しさ・悲しみ・失意等ごちゃごちゃに混ざって気持ちを収めるのも並大抵のことではない。筑後守をすぐ名乗れなかった事でこの6年余りの貞保の激しい葛藤と痛みの深さがわかる。氏貞の事情と心の内を推し量る余裕もなかっただろう。この後、宗像家を代表して秀吉のお出迎えに行くときになり、八郎貞保では公務を果たせないとして筑後守を名乗り、宗像家断絶の後には九郎右衛門と改めた。系図や宗像記の記述は是と異なるが、宗像記追考の記述が正しいだろう。 秀吉の下向
天正6年(1578年)の耳川での敗北以来大友氏が弱体化し、島津氏や龍造寺氏が勢いを増す。秋月氏も島津氏と通じて動いている。今や、九州全体が揺れ動いていた。更に中央では天正10年(1582年)に織田信長が本能寺で亡くなり、秀吉が天下を狙う。天下争乱の真っ只中に氏貞が病死した。肝心の主君を失い宗像家は迷走し始めた。周囲の敵に気づかれぬよう氏貞の死を隠すようにとの遺言が対応を遅らせる。
島津軍はすぐそこに迫り、君主不在の宗像はどちらに着いたらよいのかわからない。しかし、幸いにも、大友方の岩屋城と立花城が盾となり、秀吉の援軍が到着したことによって戦乱からはまぬがれた。 天正15年(1587年)三月、関白秀吉が薩摩討伐の為に下向するとの報せを聞いた筑前の諸将たちは、思い思いに使者を立て、出迎えに差し向けた。安芸の厳島まで上る者、上の関、或いは赤間関(山口)まで行く者、まちまちである。一方島津に組して城郭を構える者など、諸将の心はまとまらなかった。さて、立花の御家人薦野(こもの)三河守が貞保に使いをよこし、鍋島加賀守も、関白お出迎えに使者を送るそうだが、宗像はどうするのかという。道雪の家臣がやけに親しげなのも何か変だが、この薦野という人は、元は古い郷士で、大友氏の家臣ではなかった。隣郷がすべて大友氏に降参したときに大友氏に降ったが、立花に道雪が入城後、大友氏が衰退した時も独立するには家が小さく、又道雪に武勇をかわれて御家人のごとくなっていた。貞保とは元々隣郷のよしみで交流があったらしい。 貞保は早速岳山の氏貞の後室にこのことを伝えると「能(よき)に計らえ」と仰せられる。そこで、吉田入道宗金(重致)・許斐左馬太夫・石松對馬などが集まって評定することとなった。昨年より先手として遣わされた、毛利輝元・吉川・小早川の軍は豊前に討ち入り、盾突く城を次々と攻め落としているという。この状況では、宗像も関白方に味方するのが上策とのことで一致したが、さて、送る使者が難しい。とにかく貞保と吉田河内守が選出され下関に向かった。
下関に着いたは良いが、さてそれから行宛ても無い。やたらに本陣へも近づけず、きらびやかで、ものものしい上方勢の到着で周辺はごった返し、すっかり気圧されて途方にくれるばかりである。幸いにも、関白殿下の無事の到着に悦びの挨拶を差し上げようと小早川家が送った使者と出会った。そのような事ならば、浅野弾正殿を頼みとするのが良いと教えてくれる。ただし、弾正殿にも手引きが必要と、その役を引き受けてくれた。神の引き合わせと喜んで、早速この人を頼りに弾正を訪ね、翌日巳の刻、本陣において弾正の取次ぎで御前に召し出された。使者の名を尋ねられるので占部筑後、吉田河内と申しあげると、「遠路使いを上すること神妙なり。使者骨折りなりとの上意である。」と弾正殿を通して仰せを賜りその場を退出した。 秀吉の九州平定天正15年(1587年)五月、二十万の大軍を率いた秀吉に対して、島津義久は降伏した。義久は薩摩国を安堵され、五月八日には川内(せんだい=現鹿児島県薩摩川内市)の泰平寺で秀吉に謁見した。帰途、六月七日に箱崎に到着した秀吉は、「九州御国分」を行う。大友氏には豊後を安堵した。又豊前は黒田氏と森氏、肥後は佐々氏に宛行われた。更に肥前の龍造寺氏、対馬の宗氏、肥前平戸の松浦氏などには本領が安堵され、豊臣大名に取り立てられた。秀吉は備中・伯耆・備後・伊予の毛利氏領と引き換えに、豊前・筑前・筑後・肥後の四国を毛利氏に与え、九州取次ぎとする考えを持っていたが、この国替えに毛利氏が応じなかった。天正15年(1587年)六月二十五日付の朱印状で秀吉は小早川隆景から伊予国を召し上げ、筑前一国・筑後一国・肥前内、筑紫城、一群半が宛行われた。毛利氏領内の伊予を治めていた隆景を毛利氏領国から切り離し、独立の豊臣大名に取り立てたのである。 秀吉の知行宛行いには、本領を安堵する場合と国替えを行う場合と二通りあったが、筑前国内の領主はほとんど国替えされて、筑前より一掃された。立花城の立花統虎は筑後の四郡を宛行われ、筑後に国替えとなった。肥前勝尾城の筑紫広門は筑後の上妻郡に移され、原田信種・宗像才鶴(系図には残っていない。氏貞後室のことと考えられている)・麻生家氏の3名も筑後国で所領を宛行われ小早川隆景の与力となった。秀吉に抗戦した親・島津派の秋月氏は、日向の高鍋城に飛ばされた。 こうして、筑前のどちらに着くともわからない領主達は一掃され領地を取り離れた。しかし、彼等が不満分子とならぬよう、彼等と馴染みの深い毛利一族の小早川隆景に支配をまかせることで彼等を利用しようとした。又、松浦氏をはじめとする肥前国領主に対する軍事指揮権を小早川隆景と、安国寺恵瓊(あんこくじ えけい)に与えることで九州北部の海上支配権を掌握しようとした。 宗像社領と家領筑前が小早川隆景領国になった後の宗像社は、大宮司と権大宮司は欠員のまま第三の擬大宮司に宗像氏の分かれである深田氏栄が就いている。宗像氏貞までは氏栄のように社家であっても戦になれば戦場に赴いたが、これ以降社職に限られるようになった。宗像社領は二百町とされ、当初河西村、河東村、奴山が宛がわれたが、その後の交渉で奴山でなく曲村が社領とされた。二百町とは定められていたが、実際はそれよりも少なかったようである。 天正15年(1587年)6月28日付の朱印状で、秀吉は筑後で宗像才鶴に三百町を引き渡し、与力として召し置くように小早川隆景に申し送っている。 宗像才鶴とは氏貞の後室であるとされているが、「宗像記追考」によれば、秀吉奉行衆からの仰せ渡しによって秋月氏の旧領の一部である筑前国夜須郡の内二百町と上筑後の内二百町が氏貞後室に宛がわれたという。 占部氏系伝貞保の悲運
占部貞保は、勝利を手にして薩摩から引き上げる秀吉を出迎えに筑後堺へ再び罷り出た。 大和吉右衛門・石松(吉田とも)源兵衛・弘中勘助他30余人の宗像衆がはるか遠く隔たった通りの道筋にひかえる。秀吉がそれを見付けて何者かを尋ねた。宗像の家人達が自分を迎えに罷り出たと知った秀吉は、一行を先導し箱崎まで案内するよう仰せ付けられた。(大和氏は、宗像宮造営遷宮の折に断絶したが、四任の名字が消えることを嫌って、寺内豊前守秀郷の嫡子貞秀に大和姓を継がせ、その後その庶子にいたるまで大和を名乗っている。) 秀吉はこの時国分を行った。貞保と吉田河内守に奉行衆より申し渡されたのは、「筑前一国は小早川隆景に宛行われ、その内、筑前国夜須郡(現朝倉市・郡内)と上筑後高野郡の内二百町づつ、計四百町を氏貞の後室に宛行う」とのことである。貞保は筑後の瓜生野村を知行地として受けた。 この後真の太刀折紙(太刀を贈るときの目録)を以て、 占部筑後守と吉田河内守が宗像家拝領の御礼に罷り出たが、この時この両人に時の呉服一重が与えられたという。
やがて奉行より、殿下が赤間にて宿泊するのでいそぎ掃除など準備するようにとの仰せがあった。地を掃き、水を撒き、蔦が嶽の城にお迎えする。しかし、非情にも、秀吉は出立にあたって、来春までにこの城を早く破却するよう小早川隆景に下知した。隆景は乃美兵部允を遣わして、貞保に命ずる。天正16年の春、矢倉を下ろし、石垣を壊し、貞保は主君の城の破却を見届ける。延喜14年(914年)の清氏下向以来、天正15年(1587年)まで80代続いた宗像大宮司家支配の終焉であった。 代々命をかけて戦い守ってきた宗像家とその領地が、あまりにもあっけなく、風に吹かれた灰のごとくに消えてしまった。宗像家の領地がことごとく召し上げられた今となっては、後室に与えられた少しの領地では譜代の家臣達を養えるはずもない。すべて流浪の身となってしまった。その外の城主、原田・曲淵・小田部・臼杵・小金丸・杉・麻生なども家領に取り離され、朝夕の飯にも事欠く始末であったという。 領地召上げ
文禄2年(1593年)八月、貞保は家臣岩松興吉・石松清左衛門・常世神右衛門を瓜生野へ遣わし、開墾地のことを沙汰させた。さて、現在の福岡市東区にある箱崎宮では、毎年9月に「放生会(ほうじょうや)」という秋祭りが開催される。瓜生野に遣わされた3人は、途中この放生会において、名嶋の警固藤井三郎右衛門と争って討ち果たし、三人共に自殺した。この事件を取り調べるため小早川秀秋の家臣乃美備前守と草刈対馬守が送られ、文禄4年(1595年)中納言秀秋は貞保の所領を召し上げた。家系図などに返上したとの記述があり、年号も諸説あるが、文禄4年には、宗像社をはじめ氏貞後室の所領も失われているので、同時期に一緒に召し上げられたのだろう。
武勇に名を馳せた祖父や父の名に恥じまいと、懸命に闘った若き時代。宗像氏貞が大友氏と和睦したのは、貞保が20代半ばの頃であった。32歳の時氏貞の怒りをかって城への出入り差し止めとなり、その後隠居同然の暮らしとなった。38歳で筑後守を許されるも41歳の時宗像家はお取り潰し。貞保の上八の領地も召し上げられ、筑後守改め九郎右衛門と名乗る。50歳を前にして新たに受けた領地も召し上げられ、それから85歳で亡くなるまで、どの様に生きたのか...。宗像記追考を書いたと言われるが、あらゆる思いを押さえて宗像家の真実を後世に残さんとする。 寛永9年(1632年)十二月四日没。桃園宗仙居士と号す。波乱万丈の生涯であった。 | ||||
| HOME | 占部氏 | 筑前宗像争乱(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | 大城長者昔語り | ||||

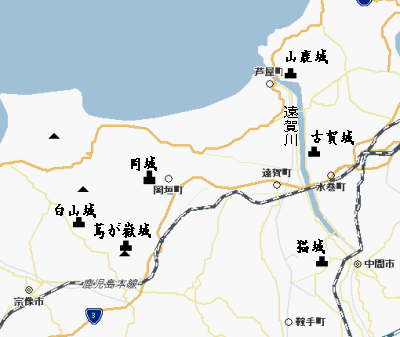 麻生氏はもともと宇都宮氏の流れであるという。現在の北九州市戸畑区、八幡西・東区、中間市から芦屋、遠賀、岡垣に至る広大な地域に勢力を張っていた。宗像氏にとってはこの地域が豊後大友勢に対する防波堤の役割をしていたが、この微妙な位置の為に麻生一族は常に大友氏と反大友氏勢力の狭間で揺れ動いていた。
麻生氏はもともと宇都宮氏の流れであるという。現在の北九州市戸畑区、八幡西・東区、中間市から芦屋、遠賀、岡垣に至る広大な地域に勢力を張っていた。宗像氏にとってはこの地域が豊後大友勢に対する防波堤の役割をしていたが、この微妙な位置の為に麻生一族は常に大友氏と反大友氏勢力の狭間で揺れ動いていた。


